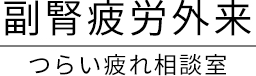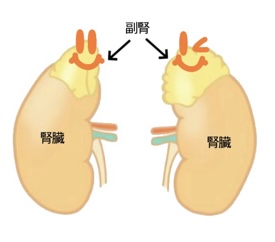「ストレス対応ホルモンの不足」なぜ起こる?【だるさ・不登校の根本原因】
朝起きられない、だるい、やる気が起きない、腹痛や吐き気、頭痛、理由のない不安、集中力が出ないなどの症状が起こる(副腎疲労の)根本原因について、お伝えいたします。
「ストレス対応ホルモンの不足」により、上記のような色々な症状が起こってきます。
この記事では「ストレス対応ホルモンの不足」を引き起こす根本原因について、ご説明していきますね。
お子さんの不登校、どうしたら良いのかと悩み続け、
「答えが見つからないうちに、時間が過ぎていってしまった…」
というお声をよくお聞きします。

安心してくつろげる空間、ご家庭でゆっくり過ごして、充電させてあげる…
お子さんを信頼して、元気を取り戻すまで温かく見守る…
とても大事なことです。
この、元気がチャージされるまでの時間、
少しでも短くできたらいいですね。
そして、元気な笑顔を、少しでも早く取り戻していただきたいです。
スーパーホルモンのおさらい
さて、不登校・慢性的なだるさの原因の中に、「ストレス対応ホルモンの不足」があります。
これは、
いろいろ負担がかかり過ぎて、ストレスの量に対して適切な量の副腎ホルモンが上手く分泌されない…
という状態のことでしたね。詳しくは、
➡︎【慢性疲労・不登校の原因】ストレス対応ホルモンの不足とは?
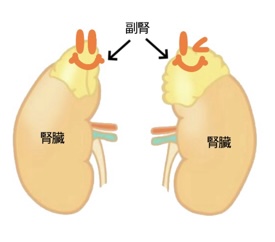
副腎ホルモンの中でコルチゾールと呼ばれるものは、一人で何役もこなす何でも屋さんで、私たちの身体や心がピンチの時に、いろいろ助けてくれています。
なので、「スーパーホルモン」と私は呼んでいます。
そして、このスーパーホルモン(副腎ホルモンのコルチゾール)の働きは、
・ストレスに対応してくれる
・低血糖にならないように血糖を上げてくれる
・炎症を鎮めてくれる
・免疫力の調節をしてくれる
・1日のリズムの調整をしてくれる
などです。
このスーパーホルモンが乱れ、不調、異常となると、
・朝起きられない
・だるい
・やる気が起きない
・腹痛や吐き気
・頭痛
・理由のない不安
・集中力が出ない
などの症状が出てきます。。。
今回は、このスーパーホルモンが、異常となってしまう原因についてお伝えしていきます。
この原因を1つでも少なくしていけば、
解決に近づくはずです!
よくある5つのストレス
スーパーホルモン(副腎ホルモンのコルチゾール)は、ストレスに対抗してくれるホルモン
でもあります。
人にとって、日々の生活の中でこの役割はとても大きいです。
お子様のストレスと言えば、
・勉強
・友人関係
・先生との関係
・学校のルール
・進路
・親子関係
などのことが、よく取りあげられます。
いろいろあります。大人と一緒、いや、それ以上かもしれませんね。

しかし、、、
ストレスとは、精神的なストレスだけではないです。
これをお読みになっている皆さんは他に、どんなストレスが、お子さんにあると思いますか?
私がよく着目するストレスには、
下記のようなものがあります。
1.栄養不足
2.過労
3.睡眠不足(睡眠の質も含む)
4.有害な化学物質
5.感染症・その他の病気
え? こんなものもストレスに?
って思いました?
これらも、ストレスになるんです。。。
そして、
・1つのストレスが強烈すぎる
・ストレスが長期間かかっている
・1つ1つは小さくても、数が多い
となると、スーパーホルモンは、たくさん必要となります。
ある時まではスーパーホルモンも量を調節して
何とか対応していますが、そのうち、需要が増えたスーパーホルモンを必要な量まで作れなくなってきます。
そして、重症化すると、需要は多いのにスーパーホルモンが最低限しか出なくなり、カラカラの状態になってしまいます。
では、それぞれのストレス要因について、もう少し詳しく説明していきますね。
1.栄養不足
現代の日本の食生活では、栄養不足なんてピンとこない!
「ウチの子には関係ないわ」というお声が聞こえてきそうです。
ですが、“新型栄養失調“の方が、大人でも子どもでも増えてます!
「新型栄養失調」???
なんじゃ?それっ?と、私も最初思いました。
一般に
体重・身長は標準範囲内のお子さん
体格の良いお子さん
ふくよかなお子さん
は「栄養状態が良い」と思われがちです。
ですが、実は、そういうお子さんでも低栄養の方がいます。
見た目で、体格はOKでも
糖質がメイン
脂質が多め
の食事をしていると、
タンパク質
ビタミン
ミネラル
が不足してきます!
見た目がOKでも、「かくれ栄養失調」があるというわけです。
「新型栄養失調」があると、
体のシステムを動かすエネルギー(電力)を
効率よく作れなくなってきます。
体の発電所が電気をうまく作れない
↓
電力不足
↓
省エネモード または 停電
この状態を
工場に例えると、停電では色んな部所の電源が入りません。
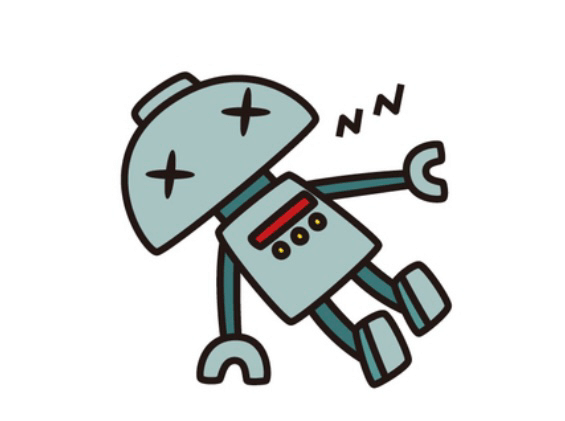
電源が入らないと、
コンピューター
=頭が働かない
ロボットが動かない
=起き上がる力が出ない
ミキサー・調理器具・掃除機も動かない
=胃腸が働かない
消化液を作る部所で、製品(消化酵素)が作れない
=消化不良、栄養素の吸収不良、便秘、下痢
腸のベルトコンベアーも動かない
=腸の動きが止まってしまう
=お腹が張って、気持ち悪い、食欲低下、便秘
これは、身体にとって、
相当な負担(ストレス)になります。
タンパク質やミネラル、それにビタミン類、、、
ざっくり言うと、この辺りの栄養が重要です。
これらの栄養素が、発電システムに必須の材料となるからです。
子供が好む食べ物には、これらの栄養素が
含まれていないことが多く、
潜在的な栄養不足のお子さんが多いです。
単に痩せていなければ、栄養不足ではない…
とはならないんですね。
体系など目に見えるものでなく、目に見えない部分で栄養が足りてるか?ということが重要です。

2.過労
子供でも、
過労となることがあります。
受験勉強や
運動量の多い部活や
習い事
遠方への通学など、
これらが、精神的にも肉体的にも大きなストレスになる場合があります。
一生懸命に、トレーニングを続けている野球少年にも、ストレス過多が、起こっていることが実際にありました。
これは、「燃え尽き症候群」とも言われたりしていますが、これも、スーパーホルモン(副腎ホルモン)の消耗が、大きく関係していると考えられます。
3.睡眠不足
睡眠時間の不足、
睡眠が浅く熟睡できていない、
日夜逆転、
など、
睡眠の質が悪くなると、スーパーホルモン(副腎ホルモン)の分泌も悪くなってきます。
睡眠の質を悪くする要因は、さまざまです。
要因の1つは、夜間の低血糖です。
甘いものや糖質の多い食事を、
普段たくさん食べていると、急激な血糖上昇の反動で、低血糖を起こしやすくなります。
そうすると、日中の低血糖の時に、ストレス対応ホルモンを使い果たしてしまいます。
(ストレス対応ホルモンは、血糖を上げる働きもするからです。)
ストレス対応ホルモンを昼間の低血糖で使い切ってしまった結果、
夜間にストレス対応ホルモン不足となり、夜の低血糖を改善できず、熟睡できなくなるのです。
ストレス対応ホルモンで血糖値が上げられない場合、体はアドレナリンで血糖を上げようとします。
アドレナリンは、戦うモードのホルモンなので、頭が冴えて眠れなくなります。
こんな理由でも、睡眠不足は起こるんです。

4.化学物質
身の回りのものから、有害な化学物質が体内に入ると炎症を起こし、スーパーホルモンが不足したり、働くべき場所でうまく作用しなくなったりしてきます。
有害な化学物質とは、
・食べ物の添加物や農薬
・クローゼットの防虫剤
・リビングやトイレの芳香剤
・クリーニング溶剤や柔軟剤
・車の排気ガス、、、
などなど、私たちの生活の中に、非常にたくさん存在しています。30~40年前と比べ、種類も量も非常に増えています。
でも、これらすべてを気にしすぎていたら、
現代で生活なんてできませんよね…
とはいえ、もし、スーパーホルモン(副腎ホルモンのコルチゾール)の適切な働きに支障が出るのなら、この辺りの化学物質についても、
真剣に考えていく必要があります。
実際、お子さんの検査をしてみると、生活の中で使われている化学物質が、体内からかなり多く検出され、驚くことが少なくありません。
そして、
身の回りの化学物質を減らしていただくようにアドバイスし、溜まってしまった化学物質については、体内から取り除いていく治療をしていくと、お子さんは、段々と元気になっていきます。
さらに重要なのは子供の時に化学物質が体内に入ってくると、影響が非常に大きくなるということです。
子どものうちに、脳を組み立てていくピースに、化学物質がはまり込んでしまうと、脳機能に影響が出てしまいます。
脳も体も完成した大人になってから化学物質が体内に入るのと違って、子供の脳神経の発達や健康へのリスクは非常に大きいのです。
なるべく早く脳が完成する前に小学生~中学生位までに、これらの毒素を取り除きたいものです。

5.感染症などの病気
感染症などの病気、
最近ではコロナ感染症など、
風邪などのウイルス感染症、
肺炎、大きな怪我、喘息、
アトピー性皮膚炎、慢性鼻炎、
虫歯、歯周病などなど、、、
これらもストレスになります。
風邪で熱が出て、熱は下がった、
風邪は治った、
なのに、その後も、
だるくて動けない、、、、
というお子さんもいます。
この病態の1つには、感染症やその他の病気でスーパーホルモンを使い果たしてしまった場合です。
感染症などの病気と戦った末に、
スーパーホルモンが、
使われてしまって不足している…
という状態です。
たいてい他にもストレスの要因が重なっていることが殆どです。
色々なストレスがベースにあり、ついに、感染症や他の病気などで、スーパーホルモン(副腎ホルモンのコルチゾール)を使い果たしてしまったという場合です。
別の病態は、感染症自体による免疫の誤作動などで炎症が続き、スーパーホルモンが不足する場合です。
これはPANS/PANDASと関係しています。
➡︎PANS/PANDASについてはこちらへ
まとめ
ストレスが重なると、
スーパーお助けホルモンの
コルチゾール(副腎ホルモン)が、たくさん必要になります。。。
短い期間、少ないストレスなら耐えられます。
ですが、
ストレスの数が多かったり、
長い期間ストレスが続くと、
もしくはストレスが強いと、
脳と副腎の連携が崩れ、スーパーホルモン(コルチゾール)の分泌がおかしくなっていきます。
また、スーパーホルモンが、働くべき場所に到達できず、働けない状態になります。
その結果、
学校に行けないような、
問題が起きてくるのです。。。。
なるべく、心の負担はもとより、体の負担になるようなものも、減らしてあげたいです。
当サイトの情報を転載、複製、改変等は禁止いたします。