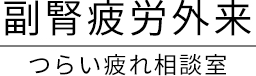不登校は親のせい?【辛い思いから脱して今できる対応とは?】
「不登校は親のせいなんでしょうか?」
「私の育て方が悪かったのかもしれない…」
そんな思いを抱えて、つらくなっているお母さんへ。
この記事は、「不登校は親のせい」と言われた経験がある方、あるいは誰にも言われていないけれど、自分を責めて苦しんでいる親御さんに向けて書いています。
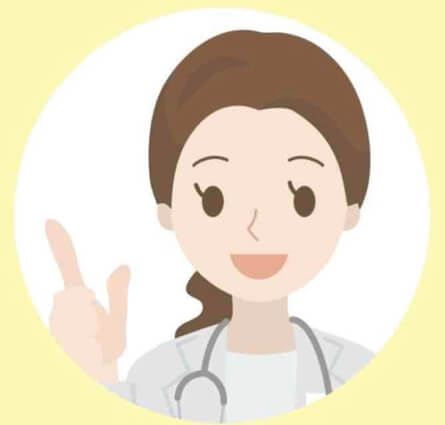
総合内科専門医の山根理子です。西洋医学的視点だけでなく、漢方を用いた東洋医学や、機能性医学を用いて、副腎疲労をはじめ、不登校のお子さんの治療や、発達のトラブルの治療を行っています。
ナチュラルアートクリニック(四ッ谷)で、不登校外来をしています。
結論からお伝えすると、不登校は親のせいと一言で決めつけられるものではありません。
不登校の背景には、学校の環境、子どもの気質、社会の変化、隠れた体の不調など、さまざまな要因が複雑に絡み合っています。
でも、そうは分かっていても、やっぱり「自分がもっとちゃんとしていれば…」と思ってしまうこと、ありますよね。
だからこそこの記事では、不登校の実態や、「親のせい」と思われがちになる背景を丁寧にひもときながら、お母さんご自身がその重たい思い込みから少しでも自由になれるよう、一緒に考えていきたいと思います。
そして、これからどうお子さんと向き合っていったらいいか…
お子さんの気持ちや体調が少しでも楽になっていくように、お母さん自身も不安や心配に押しつぶされずに過ごしていけるように…
今できることや、ちょっとしたヒントもお伝えしていきます。
「親だからこそできること」が、きっとある。
このブログが、今、悩んでいるあなたの気持ちを少しでも軽くするきっかけになれば嬉しいです。

要約
- 親のせいとは言い切れない根拠は3つ
- 不登校は親が原因だと感じたときの7つの対応
- 不登校は体からのサイン? 体の機能異常や仕組みと関係することも
- 子供に対して今できること(未来を変えるのは、今できる小さな一歩から)
- まとめ
不登校は親のせいなのでしょうか?
〜お母さんの心が、少し軽くなるように〜
お子さんが学校に行けなくなったとき、
「私の育て方が悪かったのではないか」
「もっと頑張っていれば、こんなことにはならなかったかもしれない」
そんなふうに、ご自分を責めてしまうお母さんはとても多くいらっしゃいます。
けれど、声を大にしてお伝えしたいのです。
不登校は、親御さんのせいとは言い切れないのです。
親のせいとは言い切れない根拠は3つ
それでは、3つの根拠をお伝えしますね。
不登校の子どもたちが語る「学校に行けない理由」
実際に、不登校の子どもたちに行われた調査では、次のような結果が出ています。
不安や気分の落ち込みを感じている:76.5%
朝起きられない・夜眠れない・日中眠くなる:68.9%
2023年度に公益社団法人子どもの発達科学研究所による「不登校の要因分析に関する調査研究」(令和6年)が行われています。教師、不登校児童生徒、不登校児童生徒の保護者それぞれの視点から複数回答で不登校のきっかけ要因を分析しています。
不登校の児童生徒には「あなたが最初に学校に行きづらい、休みたいと感じ始めたとき、学校や家で、次のようなときに、つらいと感じたことはありましたか。」と質問しています。この結果では不登校児童生徒の約七割が「体調不良」、「不安・抑うつ」、「居眠り、朝起きられない、夜眠れない」といった心身不調・生活リズム不調があったと回答しています。
このように、学校へ行けない理由として、子ども自身の「体や心のしんどさ」が大きく関わっていることが分かっています。
そうすると「心の問題なのかな」と思ってしまうかもしれませんが、ほかの理由が隠れていることもあります。
不安や眠れないといった状態を、「心の弱さ」や「甘え」ととらえてしまうこともありますが、
実は、こうした状態には身体の内側の不調が関係していることもあるのです。
- ホルモンバランスや自律神経の乱れ
- 栄養の不足や吸収の問題
- 「腸内環境の乱れ」や「感染症による脳への影響による理由のない不安・抑うつ」
- 「慢性的な体内の炎症」からくる疲労や免疫の不調
など…
病院の検査で異常がなくても、次のような体内の機能異常からくる不調が隠れていることがあります。
- 「体調不良」、「不安・抑うつ」、「居眠り、朝起きられない、夜眠れない」などの症状を起こしてくる「副腎疲労」
- 感染症後の免疫の誤作動が脳に影響して理由のない不安や抑うつ・気力低下を起こすPANS/PANDASという病気
よろしければ、以下の書籍をご覧ください。
こうした身体のトラブルが、気分の落ち込みや睡眠の乱れとして現れ、結果的に不登校へとつながってしまうこともあります。
決して、お子さんやお母さんの努力不足ではありません。

「子供が不登校になりやすい親の特徴・傾向」は誰もが持つ
世間ではよく、以下のような「不登校になりやすい親のタイプ」が語られています。
- 過干渉
- 過保護
- 放任主義
でも、この3つのタイプは、どんな親にも当てはまり得るものです。
子どもを心配すれば過干渉になることもありますし、忙しくて放任気味になることだってあります。
誰もが持っている“親としての揺れ”を、ひとまとめに「不登校の原因」とするのは早計です。
ただ、もしご自身に以下のような傾向があると感じた場合は、少し意識を向けてみても良いかもしれません
- お子さんに対して批判的な言葉が多くなっている
- 「ちゃんとさせたい」「世間からよく見られたい」といった思いが強くなっている
といったサインがあるようでしたら、親御さんの心が疲れていたり、焦っている証かもしれません。
まずは、ご自身を責めすぎずに、少しずつ気持ちをゆるめることから始めてみましょう。
不登校は「親のせい」という世間の思い込み

「不登校は親の育て方が原因」といった考え方は、親世代の中に根強く残っています。
「学校には行くのが当たり前」
「行けないのは甘え」
「親がしっかりしていないから」
こうした社会的な刷り込みが、親御さん自身を苦しめていることも少なくありません。
こうした考え方が、知らず知らずのうちに私たちの心に染みついています。
でも、環境的にも身体的にも、今の子どもたちが感じているストレスやプレッシャーは、私たちが子どもだった頃とは比べものにならないほど多いのです。
不登校は「甘え」や「育て方」だけで説明できるものではないということを、どうか知っておいてください。
不登校は母親が原因だと感じたときの7つの対応
不登校の子どもたちは、外では頑張れずにいるぶん、家庭の中に「安心できる居場所」を求めています。
そのとき、親御さんの心が不安やイライラ、焦りでいっぱいだと、
子どもはそれを敏感に感じ取ってしまいます。
「お母さんに迷惑かけてるかも」
「自分のせいで、家の空気が悪くなってる」
そんなふうに自分を責めてしまい、ますます心を閉ざしてしまうこともあるのです。
お母さんの“落ち着き”が、子どもに「大丈夫」を伝える
反対に、お母さん自身が少しでも気持ちに余裕を持てていると、
言葉にしなくても、子どもは
「受け入れてもらえてる」
「自分はここにいていい」
と感じられるようになります。
それではここからは、親御さんの心が少しでも軽くなり、穏やかに過ごしていただけるように、心の安定を保つためのヒントをお伝えしていきます。

1.ご自分の感情を正しく理解する
「感情を正しく理解する」って?
つらい気持ちや不安に押しつぶされそうなとき、
まずはその感情が「どこからきたのか」に、そっと目を向けてみてください。
たとえば、
「私の育て方が悪かったのかも…」と思ってしまうとき、
その奥には、「子どもに幸せになってほしい」という深い愛情があるのかもしれません。
「もっと厳しくすればよかったのかな」と自分を責めるときも、
本当は、どうにかして助けたいという願いがあるのかもしれません。
感情の表にある「不安」や「後悔」の裏には、
お母さんの優しさや一生懸命な想いがちゃんとあります。
だからどうか、
「こんなふうに感じてしまう私はダメ」ではなく、
「私はこんなにも、子どものことを想っているんだな」と、
その気持ちをやさしく抱きしめてあげてください。
それが、感情と上手につきあっていくための最初の一歩です。
2.今の気持ちを誰かに聞いてもらう
お子さんのことを考える中で、
「この気持ちを誰にも話せない」
「こんなふうに感じるなんて、私だけかもしれない」
そんなふうに感じてしまうこと、ありませんか?
でも、孤独や不安は、ひとりで抱え続けなくても大丈夫です。
信頼できる人に少し打ち明けてみるだけでも、心がふっと軽くなることがあります。

ご家族やお友達でもいいですし、もし話しにくいと感じるときは、専門家に相談するという選択肢もあります。
専門家は、お母さんの気持ちを否定せずに、やさしく受けとめながら、
整理のお手伝いや、これからのヒントを一緒に見つけてくれる存在です。
ときには、自分では思いつかなかったような視点に気づけたり、
「これでよかったんだ」と安心できたりすることもあります。
誰かに受けとめてもらうことで、感情は一人で抱えきれない重さから、少し軽くなっていきます。
言葉にすることは、それだけで心の整理につながります。
3.「完璧な親でなくていい」と許す
大切なのは、“完璧な親”を目指すことではなく、
お子さんと一緒に悩みながら歩いていくことです。
「あのときは、私なりに精一杯だった」
「今、気づけただけでも前に進んでいる」
「迷いながらも、子どもと向き合っている自分を認めよう」
そうやって、自分を少しずつ許していくことで、心のしこりが少しずつ溶けていきます。
4.そもそもの義務教育とはについて知る
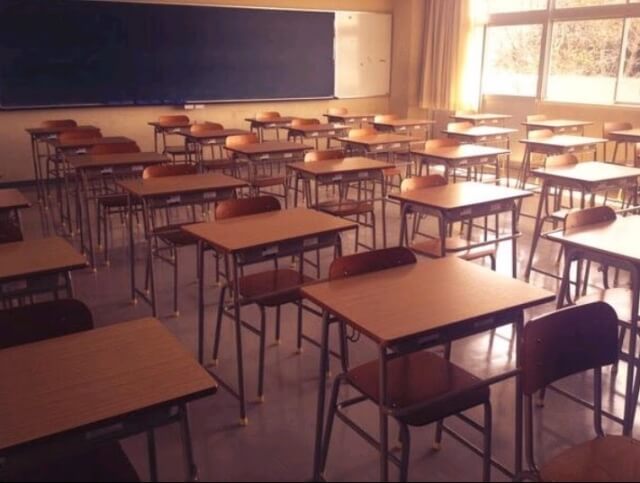
お子さんがなかなか学校に行けないとき、
「義務教育だから、行かせなければ…」
「出席日数が足りないのでは…」
と、不安になってしまう親御さんも少なくありません。
でも、「義務教育だから学校に行かせなければならない」という捉え方は、実は少し誤解があるかもしれません。
義務教育の「義務」は、子どもではなく“大人”にあるものです。
本来、義務教育とは、
すべての子どもが、等しく教育を受ける権利をもっている
そのために、国や大人が責任をもって教育の機会を整える
という仕組みです。
義務教育とは国や政府、保護者などが子どもに受けさせなければならない教育のことを指します。
日本では憲法第26条第2項にて
「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする」
と定められています。
また、教育基本法第五条では以下のような記述があります。
(義務教育)
第五条 国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。
(中略)
3 国及び地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、適切な役割分担及び相互の協力の下、その実施に責任を負う。
日本では、ある年齢の子どもに対して、
「義務」が課されているのは、子どもではなく、大人の側なのです。
一方で、子どもにあるのは「義務」ではなく、
「教育を受ける権利」です。
「義務教育」は、
子どもをしばるための言葉ではなく、子どもを守るための約束なんです。
昔は、子どもが家の仕事(農作業や家業の商売の手伝いなど)で学校に行けないこともありました。
それを防ぐために、大人が責任をもって子どもに学ぶ場を用意する、という仕組みができたのです。
学校に行けない子どもに「義務だから」と無理やり行かせることは、本来の義務教育の考え方とは少し離れてしまいます。
さらに、小学校・中学校という義務教育期間中は留年の心配はありません。
「焦らなくても卒業はできる」
そう思うだけで少し心が楽になることもあります。
5.卒業後のさまざまな進路を知っておく
どうか知っておいていただきたいのは、
「今の学校が合わなかった」ということと、「社会や将来に合わない」ということはまったく別」ということです。
文部科学省の調査では、
中学3年生で不登校だった子どもたちのうち、20歳の時点で81.9%が進学や就職をしているという結果も出ています。
『不登校に関する実態調査』~平成18年度不登校生徒に関する追跡調査報告書~(平成26年7月9日)
つまり、多くのお子さんが、それぞれのタイミングで、自分に合った道をちゃんと見つけているのです。
学びの形はひとつじゃないんです
「高校」と聞くと、全日制の高校を思い浮かべがちですが、
それだけでなく、通信制高校・定時制高校・高卒認定など、たくさんの選択肢があります。
なかでも通信制高校は、今とても注目されています。
以前は「仕方なく行くところ」と思われがちでしたが、
今は「自分のペースで学べる場所」として、前向きに選ぶお子さんも増えているんです。
通信制の良いところは、学習のペースを自分で調整できるので、
心や体に余裕を持ちながら、やりたいことを探したり、アルバイトなどで社会との接点を持ったりできること。
不登校のお子さんの中には、
「学校に行けていないのに、外に出るなんて…」
と、自分にブレーキをかけてしまうこともありますよね。
そんな気持ちを少しずつほぐしてあげることも、周りの大人にできる大切なサポートです。
そして実は、今の「学校に行けない」状態の背景には、心だけでなく体の不調やエネルギーの低下が関係していることもあります。

また、
朝起きられない、疲れやすい、集中できない――
それは体の内側のバランスの乱れが原因かもしれません。
そうした体の状態を少しずつ整えて元気を取り戻していくと、
「学校に行ってみようかな」
「何か始めてみたいな」
と、選べる未来が自然と広がっていくこともあります。
進路選びは、焦らず・親子で一緒に考えていきましょう
お子さんの気持ちや体調に余裕がでてきたら、お子さんの気持ちや考えを少しずつ聞きながら、
卒業後の進路について、ゆっくり一緒に考えていくことがとても大切です。
時間に余裕があるときは、
気になる学校の資料を取り寄せてみたり、
実際に見学に行ってみたりすることで、少しずつ進路のイメージが具体的になっていきます。
「どんなふうに学びたいのか」
「どんなことに興味があるのか」
お子さんの声に耳を傾けることで、その子らしい未来が見えてきます。
6.リラックスできる時間を確保する
お子さんが不登校のとき、親御さん自身も生活のペースが崩れたり、自分のことを後回しにしがちになるものです。
でも、親御さんが自分の生活を大切にして元気でいることは、お子さんにとっても安心材料になります。
ここでは、実際に不登校の子どもを持つ親御さんたちが、ご自身の生活を充実させるために取り入れていることをご紹介します。
毎日の中に「自分のための時間」をつくる
忙しい日々の中でも、ほんの5分〜15分でも自分だけの時間を取ることで、気持ちにゆとりが生まれます。

- 朝一杯のコーヒーを静かに味わう
- お気に入りの香りで深呼吸する
- ノートに思いを書き出す(感情の整理にも)
あるお母さんの声:
「朝、子どもが寝ているうちにベランダでひと息。空を見るだけで心がほぐれます。」
軽い運動や散歩をする
体を動かすことは、気分転換だけでなく、ストレスを和らげ、思考を整えるのにも効果的です。
- 自宅で簡単なストレッチやヨガ
- 自然の中を散歩
- 家事の合間に深呼吸しながら肩まわし
あるお父さんの声:
「夕方の散歩を日課にしています。歩くと、気持ちのモヤモヤが少し晴れてくる気がします。」
趣味や興味のあることを再開する・始めてみる
不登校になると、親は子どものことで頭がいっぱいになりがちですが、自分の楽しみをもつことは大切です。
- 手芸、ガーデニング、読書、音楽、料理オンラインで学べる趣味講座や資格取得絵を描く、文章を書くなどの表現活動
ある親御さんの声:
「昔好きだった刺繍を再開しました。無心になれる時間が心のリセットになっています。」
「ヨガに行って、自分の状況を知らない方の会話やヨガに集中して頭が空っぽになることでその時間は悩みが消え、汗を流してスッキリした気持ちになります。」

不登校の子どもに寄り添う親御さんは、本当にたくさんの思いを抱えてがんばっています。
でも、「子どものため」と思って自分を後回しにし続けると、気づかないうちに心がすり減ってしまうことも。
お子さんの元気は、親御さんの心の余裕からも育まれます。
だからこそ、あなた自身の時間や気持ちも、ぜひ大切にしてあげてくださいね。
7.自分にも「このままで大丈夫」と声をかけてあげる
不登校のお子さんを支える毎日は、とても大変で、「もっと頑張らなければ」と自分を責めてしまうこともありますよね。
そんなときこそ、まずはお母さん自身に「今のままの私で大丈夫」とやさしく声をかけてあげることが大切です。
自分に優しい言葉をかけることで、心が少しずつ軽くなり、疲れた気持ちもほっと落ち着いていきます。
完璧である必要はなく、時には「今日はよく頑張ったね」と自分を認めてあげることが、自己肯定感を育てる大きな一歩になります。
また、つい「できていないこと」や「足りないこと」に目が向きがちですが、
「今日をなんとか過ごせた」
「子どもに笑顔で話しかけられた」
などの小さなできたことにもぜひ目を向けてみてください。
たとえば、
「今日は少し余裕を持って朝を迎えられた」
「今日は一度も怒らずに話せた」
「子どもが笑ってくれた」
といったことを見つけて、自分で認めてあげることがとても大切です。
そうした日々の積み重ねを「できたことノート」に書き留めるのもおすすめです。
自分の頑張りを見える形にしておくことで、つらい時でも
「私、ちゃんとできてる」
と自信を持ちやすくなります。
お母さんが自分を大切にできるようになると、そのやさしさは自然とお子さんにも伝わり、家族みんなの心の安定につながっていきます。
どうか自分を責めすぎず、今の自分をまるごと受け止めてあげてくださいね。あなたは、もう十分に頑張っていますよ。

不登校は体からのサイン? 体の機能異常や仕組みと関係することも
不登校の原因はひとつではなく、さまざまな身体や心の影響が関わっていることがあります。
ここでは、その中でも特に気をつけたい3つのポイントについてお話ししますね。
まず「副腎疲労」というものがあります。副腎はストレスに対処するための大切な臓器ですが、長く強いストレスが続くと疲れてしまい、体や心のエネルギーが不足しがちになります。
そうすると、疲れやすくなったり、気持ちが落ち込みやすくなったりして、学校に行くことが難しくなることがあります。
次に、「感染症の影響」も見逃せません。体の中に見えないウイルスや細菌の影響が続くと、体はずっと戦い続けるために疲れてしまいます。
体の不調や頭がぼんやりする感じが続くと、心も元気を失いやすくなり、不登校につながる場合があります。
そして、「原始反射の残存」という体の発達の問題もあります。
赤ちゃんの頃に自然にできていた体の動きや反射が、大人になるまでにきちんと消えていないと、体のバランスや集中力が取りにくくなることがあります。
これが心の不調や学校生活の困難に関係していることもあります。
これらは体と心が深くつながっているからこそ起こることで、それぞれに合ったケアや対策をすることで、お子さんのつらい状況を改善できる可能性があります。
心配なことがあれば、専門家に相談してみるのも一つの方法です。
「副腎疲労」や「感染症によるメンタルへの影響」、原始反射については、下記の書籍で分かりやすく詳しくご説明しています。
子供に対して今できること
まずは、お子さんの心と体がゆっくり休めるように、元気を取り戻すことを一番に考えてあげてください。
焦らず、安心できる時間を過ごすことが、これからの回復への大切な一歩になります。
「学校を休んでもいい」と伝える、「学校に行きなさい」は禁句
お子さんに今できる、いちばんのサポートは「安心感」を届けることです
お子さんが学校に行けなくなったとき、まずは
「学校を休んでもいいんだよ」
と、安心できる言葉をかけてあげてください。
「学校に行きなさい」と言ってしまいたくなる気持ちも、親としては自然なこと。
でも、子どもにとってその言葉は、
「行けない自分はダメなんだ」
と感じてしまうきっかけになってしまうことがあります。
お子さんが1日中家にいても、
「今はそういう時期なんだね」
と、まずは受け止めてあげることがとても大切です。
そしてぜひ、こう伝えてあげてください。
「学校に行かなくても、あなたの価値は変わらないよ」
このひと言が、お子さんの心に安心と自己肯定感を育ててくれます。
親御さんからの無条件の愛情と理解は、回復の一歩を踏み出す大きな支えになります。

不登校の原因は追求しない
不登校の原因を無理に追求しなくても大丈夫です
お子さんが学校に行けない理由を知りたいと思うのは当然のことですが、
多くの場合、本人もはっきり言葉にできなかったり、自分でもわからなかったりします。
無理に理由を聞き出そうとするよりも、
「今は安心して過ごせること」
が何より大切です。
「理由がわからなくても大丈夫。あなたのことを信じているよ」
そんな言葉が、お子さんにとっての安心になります。
子どもを信じる
信じたいけれど不安になるのは当たり前です
「このままで大丈夫かな…」
「将来、どうなってしまうんだろう…」
そんな不安が消えないまま、お子さんを信じ続けるのは、簡単なことではありません。
信じたい気持ちと、不安に押しつぶされそうな気持ちの間で揺れ動くのは当たり前です。
不安になるのは、子どもを大切に思うからこそ。
よく、「信じるって、心配しないこと?」と思われがちですが、
実はそうではなくて、
「心配しながらも、その子の力を信じる」
ことなのです。
「この子はこの子のペースで、きっと前に進んでいける」
子どもは本当に、思っている以上にしなやかで強さを持っています。
今は立ち止まって見えるかもしれませんが、
しっかり休んだ子は、いつか自分のタイミングで動き出す力を持っているのです。
お子さんにとっても、親御さんが「信じているよ」と思ってくれていることは、
目に見えなくても、心の深いところに届いています。
「何があっても味方でいてくれる」
「今の自分でも大丈夫だと思ってくれている」
そんな安心感が、子どもの回復力を支え、前に進む力になります。
不安があっても、子どもの力を信じようとする気持ちがあるだけで十分です。

子どもの話をよく聞き気持ちを受け入れる
お子さんの気持ちを受け止めるために大切なのは、無理に言葉を引き出そうとするのではなく、安心して話せる環境を作ることです。
お子さんと向き合うときには、
「そんなことで?」
「我慢しなさい」
といった言葉がつい出てしまうこともあるかもしれませんが、
もし余裕があるときは、
「そう思ったんだね」
と、お子さんの気持ちをそのまま受け止めてあげる声かけを意識してみても良いかもしれません。
また、何か言葉をかけたいときも、すぐにアドバイスや正解を示すのではなく、
「そう感じたんだね」
「つらかったね」
と気持ちに寄り添う言葉をかけると、お子さんが安心できることもあるようです。
すぐに返事が返ってこなかったり、沈黙の時間が続いたりしても、焦らなくて大丈夫です。
何も話さなくても、そばにいてくれる存在がいることで、子どもの心は少しずつほどけていくことがあります。
そしてもし、お子さんが言葉にしてくれたときには、その言葉を繰り返したり言い換えたりして、
「こういうことかな?私の理解は合ってるかな?」
と静かに確認しながら聴くこともひとつの方法です。
こういったやり取りが、子どもに
「わかってもらえた」
という感覚を育て、少しずつ自分の気持ちを整理する手助けになることもあります。
正論で子どもを責めない
「正論で責めない」というのは、たしかに“正しいこと”ではあるけれど、
それを子どもに一方的にぶつけると、心が閉じてしまうような言い方を避ける方がいいです。
親としてよく言ってしまう正論の例は
「学校は行くものなんだから、頑張って行きなさい」
「みんなちゃんと行ってるよ。あなたも甘えてちゃダメでしょ」
「このままじゃ将来困るよ。高校にも行けなくなるよ」
「理由も言えないなんてわがままじゃない?」
正論はたしかに「間違ってはいない」ことが多いのですが、
子どもがつらさの中にいるときに言われると、責められた・否定されたと感じやすくなります。
特に不登校のお子さんは、すでに「行けない自分」を責めていることが多いので、
そこに正論を重ねられると、余計に追い込まれてしまうことがあります。
大切なのは、気持ちに寄り添うこと
まずは
「行けなくてつらいよね」
「どうしたら少しでも楽になれるかな」
と、お子さんの心にそっと寄り添ってあげることが、回復の第一歩になります。

子どもを安心させ、子どもの自己肯定感を上げる
「存在そのもの」を認める言葉をかける
「できた」、「できない」ではなく、
「あなたがいてくれること自体がうれしい」と伝えることが大切です。
例えば
「あなたと過ごせてうれしいよ」
「ただそばにいてくれるだけで安心するよ」
子どもは「自分は愛されている」と感じられることで、自己肯定感の土台が育ちます。
できないことや苦手なことを指摘しない、できるようになったことをほめる
つい口から出てしまいがちな言葉に、こんなものがあります。
- 「どうしてまた片付けてないの?」
- 「なんでこんな簡単なこともできないの?」
- 「また途中でやめちゃったの?」
こうした“できていないこと”を指摘する言葉は、親としては改善してほしい気持ちから出てくるものですが、子どもにとっては「否定された」「責められた」という感覚だけが残ってしまうことがあります。
繰り返されるうちに、「自分はダメなんだ」「どうせまた怒られる」と思い込むようになり、やる気や自信がどんどん失われてしまうこともあるのです。
では、どうすればいいのでしょうか。
たとえ小さなことであっても、「できたこと」「やろうとした気持ち」に目を向けて、言葉でしっかり伝えてあげることが大切です。
たとえば…
- 「ご飯茶碗を片付けてくれてありがとう。助かるよ。」
- 「今日はしっかりご飯が食べられたね。嬉しいな。」
- 「好きなことをやってみようって思えたんだね。すごいじゃん!」
今まではできなかったことが少しでもできるようになったとき、
あるいは、ほんの少しだけでも前向きになれたとき、
その瞬間を見逃さずに褒めてあげることで、子どもは「認められた」「役に立てた」と実感できるようになります。
その体験の積み重ねが、自己肯定感を育てる大きな力になります。
できないことではなく、「できたこと」に目を向ける。
その視点を意識するだけで、親子の関係も、子どもの心の元気も、少しずつ変わっていきます。
子どもの「気持ち」を受け止める
感情を否定せず、
「そう思ったんだね」
と受け止めると、子どもは安心して自分を出せるようになります。
例えば
「悔しかったね」「イヤだったよね」
「そう感じるのは自然なことだよ」
感情を受け止めてもらえる経験が、「自分を認めていいんだ」と感じる力になります。
自己肯定感は「安心できる関係」から育ちます
子どもは、親や身近な大人との関係の中で「自分は大丈夫なんだ」と感じられるようになります。
親の気持ちを安定させ、こどもへ負担を与えないようにする

お子さんが不登校のとき、親御さんの心も揺れたり疲れたりしますよね。
でも、そんなときこそ 「自分のことを大切にする時間」が、親御さん自身の元気につながります。
無理に大きなことをする必要はありません。
日常の中に、小さな「自分時間」を少しだけ加えてみませんか?
また、上記の「不登校は母親が原因だと感じたときの7つの対応」の方法も試してみてください。
医学的な面からお子さんにしてあげられる対策
毎日の食事の準備は大変なことも多いと思いますが、無理せずできる範囲で、こんなことを心がけてみるとお子さんの体にも心にも優しいサポートになります。
甘いもののとりすぎが体に与える影響
甘いお菓子やジュースは、ほっと一息つきたいときや、疲れているときの癒しになりますよね。
ただ、とりすぎてしまうと、体や心に少しずつ負担がかかることもあるんです。
どんな影響があるの?
気分の波が激しくなる
→ 糖分で一時的に元気になりますが、血糖値の変動が激しくなるため、そのあと急に疲れたり、イライラしたりすることがあります。
集中力ややる気が落ちやすくなる
→ 血糖値が急上昇した後急降下するため、「なんとなく元気がない」「やる気が出ない」と感じることも。
疲れやすくなる、朝がつらくなる
→ 血糖値を調節する臓器が疲れてしまい、体がだるくなる原因に。
腸内環境が乱れる
→ 悪玉菌が増え、便秘やお腹の不調につながることがあります。
ビタミンBの消費が激しくなる
→気持ちの変動や疲れやすさにつながる
甘いものへの対策です。
「量」と「頻度」を見直すことが、体にやさしい第一歩です。
・毎日食べるのではなく、「週に◯回」と決める
・ジュースをやめて、お茶や水にする
・手作りのおやつにして、砂糖の量を調整する
・果物や干し芋など、自然な甘さを楽しむ
などを試してみてください。
添加物のとりすぎが体に与える影響
忙しい日々の中では、加工食品やお惣菜などに頼ることも。
添加物自体がすべて悪いわけではありませんが、とりすぎが続くと体に負担をかけてしまうことがあります。
どんな影響があるの?
腸のバランスが崩れやすくなる
→ 善玉菌が減って、免疫力が下がったり、肌荒れや疲れにもつながります。
アレルギー症状が出やすくなる
→ 敏感なお子さんでは、湿疹や鼻炎などの原因になることも。
メンタルへの影響
→ 人工甘味料や合成着色料の過剰摂取は、気分の落ち込みや集中力の低下に関係すると言われています。
→多くの食品にに使われているリン酸塩系の添加物は体内のマグネシウムや亜鉛、カルシウム、鉄などのミネラル欠乏を招き、やはり情緒の不安定さの原因になります。
体が疲れやすくなる
→ 添加物の分解・排出に肝臓や腎臓に負担がかかるため、慢性的な疲れが出やすくなります。
できることから少しずつで大丈夫です。
添加物を「完全に避ける」のは、今の時代なかなか難しいことです。
でも、ちょっと意識を変えるだけで、体への負担を減らすことはできます。
たとえば…
・加工食品やコンビニ食を減らし、手作りや自然な食材を増やす
・原材料表示を見て、添加物が少ない商品を選ぶ
・特にお子さんには、お菓子やジュースの量を控えめにする
ビタミンB群を意識した食事のすすめ
お子さんの心と体の調子を整えるために、「ビタミンB群」はとても大切な栄養素です。
食事はちゃんと食べているのに
「朝がつらそう」
「なんだか元気が出ない」
「イライラしやすい」……
そんな時には、ビタミンB群が不足しているサインかもしれません。
ビタミンBの消費が激しい、または、ビタミンBの含まれる食べ物が少ない、腸内細菌が乱れているなどの原因が考えられます。
ビタミンB群ってどんな働き?
ビタミンB群は、ごはんやパンなどのエネルギー源を、体が使える「元気のもと」に変えるお手伝いをしてくれる栄養素です。
でも、体にためておくことができないため、毎日の食事から少しずつ補ってあげることが必要なんです。
また、ビタミンB群は脳や神経の働きを支え、気持ちを安定させる役割もあります。
「疲れやすい」「やる気が出ない」「落ち込みやすい」そんな心の不調にも、実は関係していることがあります。
ビタミンB群がとれる食材の一例
豚肉・鶏肉・レバー:B1やB6が豊富で、疲労回復に◎
卵や魚:バランスよくビタミンB群が含まれています
納豆・豆腐・味噌などの大豆製品
緑の野菜(ほうれん草、ブロッコリーなど)

お子さんの心と体は、食べるものからつくられています。
子どもたちの元気や情緒の安定には、食べものが意外と大きく関わっています。
「できることから少しずつ」で大丈夫。
お母さんが無理なく続けられる工夫が、お子さんの笑顔につながっていきます
学校に行かなくても学べる
不登校でも、お子さんは学校に行かなくてもいろいろな方法で学べます。
大切なのは、お子さんのペースで無理なく進めることです。
例えば、自宅で教科書やワークを使って学んだり、オンライン授業で好きな時間に勉強したりする方法があります。
また、フリースクールや教育支援センターといった学校以外の居場所で学ぶこともできます。
将来的には通信制高校なども選べます.
親御さんは
「今のままでも大丈夫」
「あなたのペースでいいよ」
と安心させてあげることが一番の支えになります。
学びの形は一つではないので、お子さんに合った方法をゆっくり探していきましょう。
- オンライン学習
インターネットを使って、自分のペースで勉強できるサービスです。
小・中学生向けの動画授業や、問題集付き教材サイトがたくさんあります
ゲーム感覚で学べるものもあり、楽しみながら取り組めます
Zoomやアプリを使って、先生とリアルタイムでつながる授業も - フリースクール
学校以外の学びの場で、安心して通える子も多いです。
子どもの気持ちや個性に寄り添ってくれる
勉強だけでなく、遊びや人との関わりも学べる
通っても出席扱いになる場合もあります(自治体により異なります) - 適応指導教室(教育支援センター)
自治体や教育委員会が運営する学びと居場所の場です。
少人数で、ゆっくり慣れていける環境
学校とは別の場所だけど、連携して学びを進められることもあります - 通信制の中学校・高校(将来的な選択肢)
不登校を経て、中学卒業後に利用できる学びの場です。
自分のペースで学べる
高卒資格を取得したり、進学・就職の道も選べます
最近は、学び+カウンセリングがある通信制高校も増えています。
焦らない対応を心がける
不登校のお子さんに対しては、焦らずゆっくり向き合うことがとても大切です。
無理に学校へ行かせようとしたり、急いで変化を求めると、お子さんが余計にプレッシャーを感じてしまうことがあります。
まずは、お子さんの気持ちやペースを尊重し
「今はこういう時期なんだね」と受け入れてあげること。
安心できる環境を作ることで、少しずつ心が落ち着き、前向きな気持ちが育ちやすくなります。
焦らず待つことで、お子さん自身が自分のペースで少しずつ元気を取り戻し、将来に向けた一歩を踏み出せるようになるのです。
親御さんも気持ちを楽に持ち、温かく見守ってあげましょう。
まとめ
不登校は「親のせい」と一概に言い切れるものではありません。
多くの調査から、不登校の原因には子ども本人の不安や体調の問題、環境とのミスマッチなどさまざまな要素が関わっていることがわかっています。
親御さんの育て方だけが原因ではなく、誰にでも起こり得る問題なのです。
だからこそ、親御さんが自分を責めすぎず、まずはお子さんの心と体の健康を大切に見守ることが大切です。
また、焦らずお子さんのペースを尊重し、安心して話せる環境を作ることも効果的です。
必要に応じて専門家のサポートを受けながら、親子で一緒に前に進んでいきましょう。
親御さん自身の心も大切にし、無理せず自分の時間や気持ちのケアを忘れないことが、結果的にお子さんを支える力になります。
不登校は、決して親御さんの「責任」ではありません。現代の生活では、心や体に負担をかけるストレスや環境の変化が大きく影響することがあります。
お子さんのつらい気持ちや状態には、それぞれに合った対応をしていくことで、その期間が短くなる可能性も十分にあります。
ナチュラルアートクリニック(四ッ谷)不登校外来
山根 理子