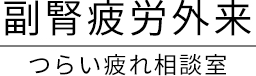『つらい疲れ相談室サイト』運営責任者
山根 理子(やまね りこ)
経歴
- 総合内科専門医、循環器専門医、漢方専門医。日本大学医学部卒業、同大学院内科学講座循環器内科学医学博士号取得。
- 循環器内科勤務とともに東洋医学科での研修も行う。さらに、分子栄養療法や機能性医学の専門知識を深め、従来の西洋医学では解決が難しい多様な症状にも対応する。
- 多忙な日々を過ごす中、自分自身がどうにもならない重い疲労感に悩まされた際、日本初の副腎疲労外来を開設した本間良子医師のバイオメディカル治療で驚異的な回復を遂げ、その治療法に深く感銘を受ける。
- 現在は、自身の外来でも最新の海外の検査を用いた同治療法を取り入れ、副腎疲労をはじめ、不登校のお子さんの治療、発達のトラブルに対する治療、不妊治療・一般的な治療で改善の見られない不調に対する治療を積極的に行っている。
- お子さんの発達に関するお悩みに対しても、副腎疲労の治療アプローチが有効であることを学び、現在は機能性医学による薬に頼らない治療に取り組んでいる。
- 自身も子育ての経験をしており、親御さんが日々抱えていらっしゃるご不安やご苦労を身をもって実感している。その経験を活かしながら、安心してご相談いただけるよう、心を込めて診療にあたっている。
- ナチュラルアートクリニック(四ッ谷)で、不登校外来 をしています。
朝なかなか起きられないのは…
体の中で「エネルギー作り」がうまく出来ていないことが原因になっている場合があります。
このエネルギーがしっかり作れるようになると、体の中のエンジンがかかりやすくなり、少しずつ体も心も元気を取り戻していきます。
朝の目覚めや日中の活動が楽になっていくことで、「自分は大丈夫」と思える自信や、気持ちの安定にもつながっていきます。
「長引くだるさ」から、私が抜けだせたのは?
私自身が患者として、「副腎疲労の第一人者」と言われる複数の医師に診察を受けた経験から、主治医の選択は非常に重要だと痛感しています。
同じ副腎疲労の状態に対して、主治医によって治療方法やアプローチが全く異なり、その効果に大きな差が現れるからです。
さらに、信頼できる主治医にサポートを受けているという安心感が治療効果に大きく関わります。
さて、「長引くだるさ」から抜け出す秘訣ですが…
大きく分けて2つあります。
1つ目は、燃料となる栄養素を正しく入れ、身体のエンジンがかかりやすくなるような調整です。
2つ目は、身体の機能低下の原因(疲労の元凶)を減らすことです。体に負担をかけているもの(体内の炎症など)を取り除くアプローチが、回復への大きな鍵となります。
バイオメディカル検査で疲労の元凶をみつけだし、検査結果に基づいて、原因を効率的に排除することで、回復スピードもアップします。
備考欄に、「山根医師への問合せ」とご記載ください。
ナチュラルアートクリニック(四ッ谷)不登校外来
下記書籍を出版いたしました。
思いもよらない不登校の原因や、副腎疲労についての説明と対策について記載しております。
ブログの内容をより充実させ、症例を挙げて詳しくご説明しています。
もしよろしければ、ご一読ください。
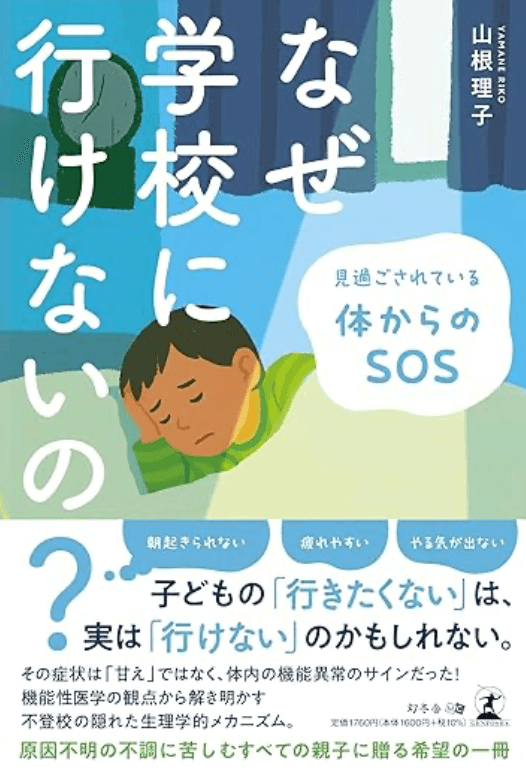
目次
はじめに
序章 不登校の実態
第一章 副腎疲労とは何か
【ケース① 軽度の副腎疲労】朝だるくて起きられず学校を休みがちになってしまったA子さん
ストレス対応ホルモンが不足する副腎疲労
「ストレス対応ホルモン」とは
副腎疲労のメカニズム
【ケース② 重度の副腎疲労】だるさが少しずつ強くなり、お昼まで目が覚めずベッドから起き上がれなくなってしまった高校生のB子さん
副腎疲労でこんなにいろいろな症状が……
原因となるメンタル以外のストレス
副腎疲労を診断するための検査や治療
登校はどうしたらいい?
第二章 副腎疲労に関連する疾患
【ケース③ 新型コロナウイルス後遺症】新型コロナウイルスに感染後、学校に行けなくなった小学5年生のCさん
新型コロナウイルス後遺症
回復を促すために
【ケース④ 風邪が引き起こすメンタル疾患】ある時から急に、不安感、食の好みの急激な変化、学習障害がみられた中学生のDくん
感染症が引き起こすメンタル疾患とは
早期の原因検索・治療が重要
感染症が引き起こす起立性調節障害POTS
POTSの治療法
【ケース⑤ シックスクール症候群】週初めに登校できなくなってしまう小学3年生のEさん
学校の環境が合わない原因
【ケース⑥ 感覚過敏】教室の中が大音響の鳴りやまないライブ会場のように感じられてつらい小学3年生のFくん
教室内は刺激が強過ぎる
【ケース⑦ モロー反射】消えるはずの赤ちゃんの反射が残っているせいで、不安になるGさん
原始反射の残存(赤ちゃんの時の反射が残っている)
モロー反射
モロー反射から卒業するためのエクササイズ
原始反射の卒業に昔ながらの遊びを
【ケース⑧ ギフテッド】「学校では真っ白な部屋の中に何もすることがない状態で閉じ込められて、ただじっと座って我慢しなければならない感じ」と言うHくん
ギフテッド児とは
ギフテッド児が学校に行かなくなる理由
第三章 症状を和らげるためにできること どの症例にも対応する家でできる対策(子どもを守る食事/睡眠の大切さ/知らぬ間に体に入る有害な環境化学物質から子どもを守る)